軌道のずらし方 触る場所
ここまでドリブルにおいては、ボールに接触する前の予想進路と実際の進路が異なることが重要であることを見た。
これは相手を抜く前のアプローチにおいても重要であり、同サイドの変化から抜くためにも重要であり、抜いた後が次のアプローチにつながるという意味でも重要であった。
ここでは、予想と実際の進路をずらすための動きについて見る。
最も単純な状況では、足が入る方向とボールが飛ぶ方向は一致する。
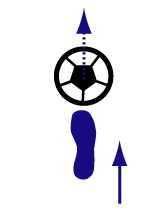
足が入る方向にボールが飛ぶと予想され実際にもその方向に飛ぶ。
ここから足の入れ方を変え、接触点を変えれば飛ぶ方向は変わる。
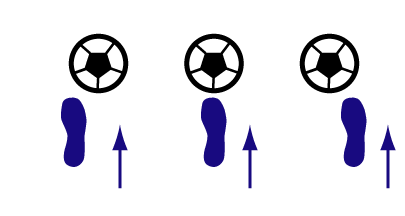
また同じ方向から足が入っても足の向き、もしくはその形で飛ぶ方向は変化する。
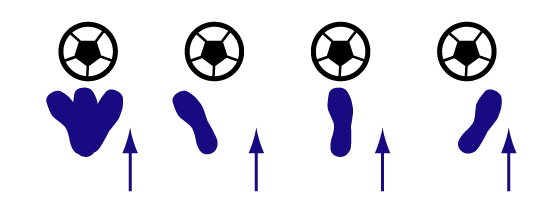
具体的には以下のようである。












ボールの中心より内側につま先を内側に入れた状態で触れる。


ボールはアウト側へと飛ぶ。


ボールとの接触点を変えることで、ボールの飛ぶ方向は変わる。
類似した動作から接触点を変えることができれば、予想進路と実際の進路をずらすことができる。
このため接触点を変える技術はドリブルにおいて重要となる。
接触点を変える方法の一つは、体全体の重心を移動させることである。
右足でボールに触る場合を考える。
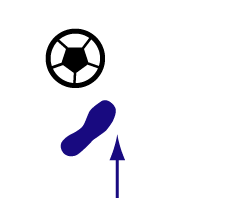
この時、体を支持する左足で重心が右に動くように地面を踏む。
重心が右に動けばそれにともない右足も右に動く。
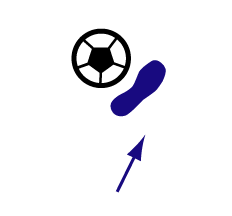
それにより触る場所を変えることができる。
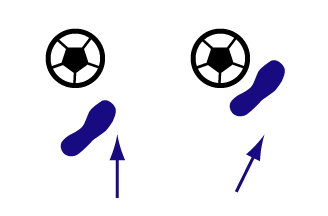
具体的には以下のようである。















最初、足はボールに対して縦に入るように見える。



実際には外側から触れる。




この過程で重心はアウト側、保持者から見て右側に動いている。




踏み切る方向によりボールとの接触点をずらしている。
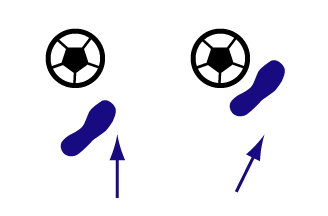
次も同様である。














地面を踏む方向、踏み切る方向を変えることで接触点をずらすことができる。
次に膝の向き、もしくは配置を変えることで接触点をずらす動きを見る。
例えば足をボールに近づける途中、膝を外に向ける。
膝の伸展方向が外に向くため足の軌道は外にずれる。
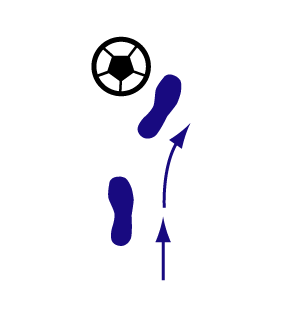
具体的には次のようである。
















最初膝は正面方向を向いている。


接触までの過程で膝はより外側を向く。




これにより足はボールの外側へ動く。
外側を触れることによりボールはイン側に動く。



膝を内側に向ける例は次のようである。
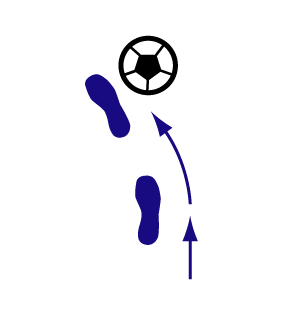
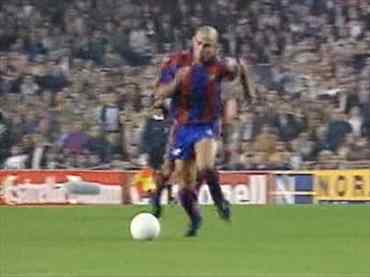
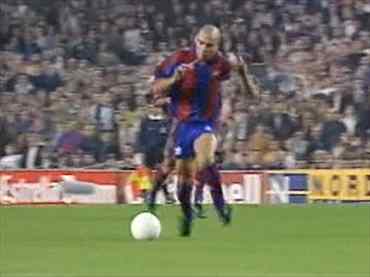
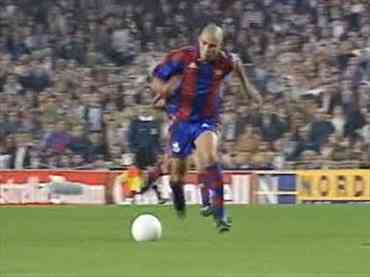
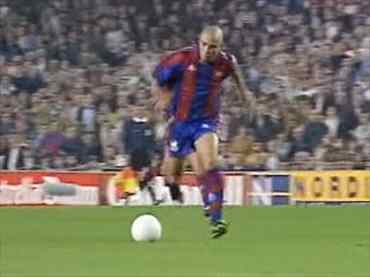
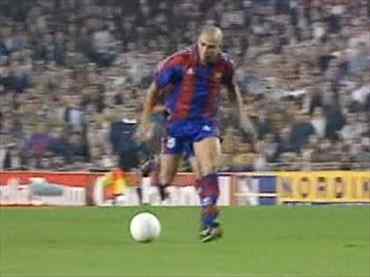

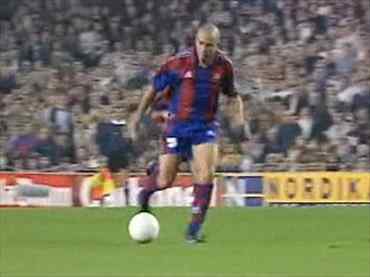
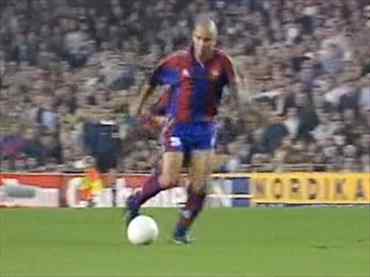
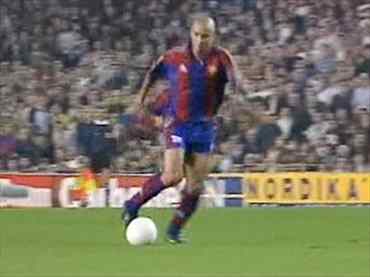
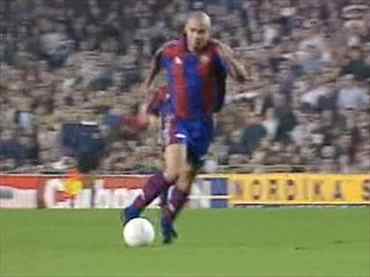
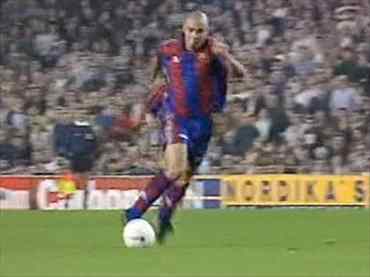
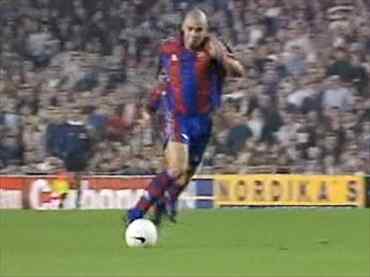
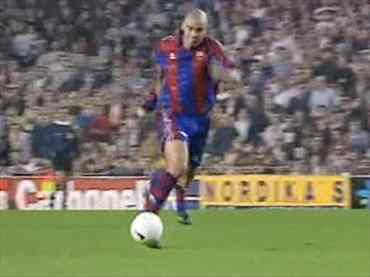
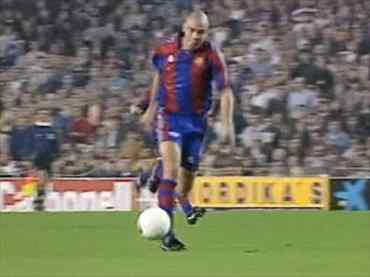
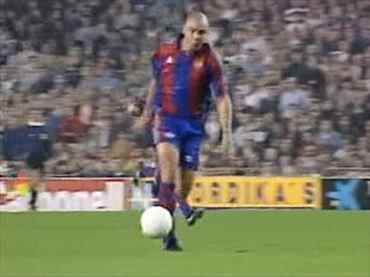
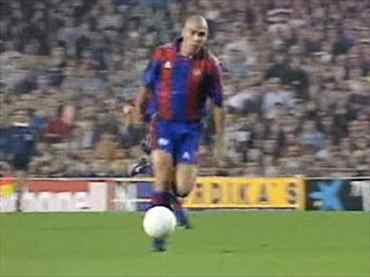
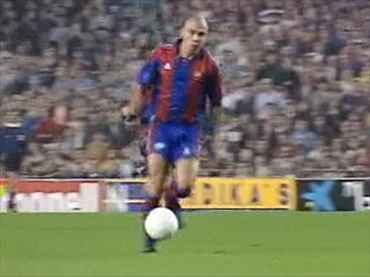
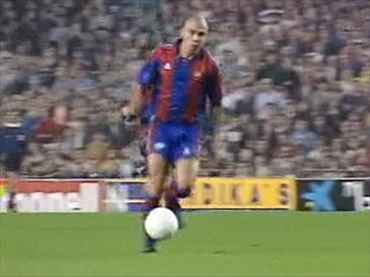
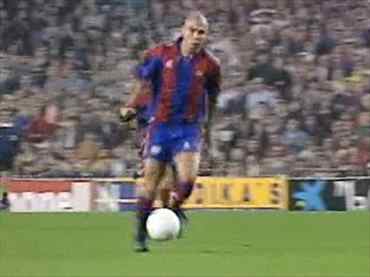
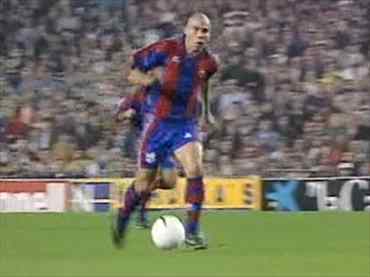
膝が内側を向いている。
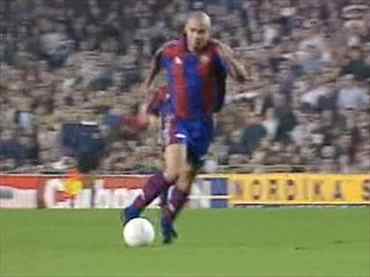
この動きがあることで、ボールとの接触点は変化する。
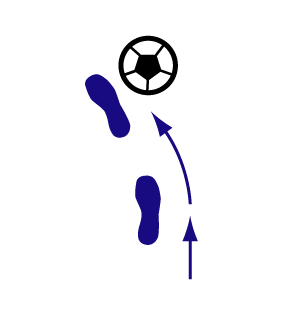
次も膝の動きによりボールとの接触点を変える例である。













接触前の膝の動きは次のようである。




最初、膝は下を向いている。

そこから膝を内向きに持ち上げる。



膝がボールの内側に触れやすい位置に来ている。
ここから支持足を左前方に伸ばし、ボールに触れる方の膝を伸展させながらボールに触れる。



膝の位置、もしくは膝の体に対する相対的な配置を変えることにより接触点を調整している。
次はキックフェイクから触る場所を変える例である。
























足は最初、ボールの後方から近づくように動く。



その後、軌道が変わる。



横方向から接触している。
膝の位置、もしくは配置を変えることにより接触点を変えている。



以上のように膝の向き、もしくは配置を変えることで接触点をずらすことができる。
接触点をずらすという意味では、ボールに触れないこともそれに含まれる。
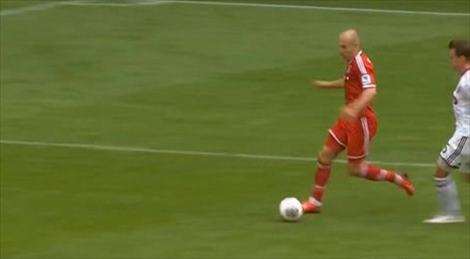










この角度からはボールに触れたようにも見える。

しかし実際は全く触れていない。









触れると見せて触れないことは、予想と実際のボール進路をずらすことにつながる。
このため、空振りと呼ばれる動作はドリブルにおいて重要な意味を持つ。





保持者はアウト側へ触るモーションからボールに触れていない。



これに対して24番の守備者は次のように反応する。




画面左に反応している。
仕掛ける前に相手を崩す場合など、ボールに触らない動きは有効である。
以上では、予想進路と実際の進路をずらすため接触点を変えることを見た。
次に接触点が同じでボールの軌道を変えるための動きを見る。
股関節の操作で得られた重心移動と体幹の動きで生み出した膝下への螺旋の力をうまく伝えている好例ですね。
いやはやいつも素晴らしい画像をありがとうございます。
2015/03/11 08:03 - てんせぐりてぃ
【蹴球計画】より ※この内容は蹴球計画のミラーサイトとして作成しています。詳細についてはこちら。